急に運動を始めたとき、再開したときに膝やふくらはぎが痛くなりませんか?
みなさん、こんにちは。
ヤジコヤデザインの矢島(代表)です。
ヤジコヤデザインではコーディングなどのデスクワークをしておりますが、実は理学療法士としてリハビリの仕事もやっております。
そんなリハビリ職の視点から、さまざまなカラダのお悩みに役立つ情報をお伝えしていきます。
さて、皆さんは急に運動を始めたときや、再開したときに膝やふくらはぎを痛めてしまうことってありませんか?
私はあります!
健康や体型維持、ダイエットのためにせっかく運動を続けていても、仕事が忙しくなってくるとどうしても運動ができなくなってしまう時期がありますよね。
やっと時間ができて、再開してみると次の日から膝やふくらはぎが痛くて、ちょっと大変(;~~)
そんな経験があります(理学療法士なのに)。
今回は、そんな痛みが起きてしまった後の対処方法などを私の経験も交えてお伝えしたいと思います。
前回までは体の仕組みとか解説が多かったかなと思いまして、今回はそう言った部分は少なめです。
痛みが起きてしまう場所と対処方法
私は軽いヨガ(体は依然として固いですが)とエアロバイクを体力維持のために週に3~4回ほどやっています。
ただ、時々やっぱり外で運動したくなるんですよね。
それで、久々にテニスの壁打ちをやったり、ランニングに出てしまうとついついやり過ぎてしまって、膝やふくらはぎに痛みが出てきてしまうなんてことがあります。
そのまま運動を続けてしまうとさらにケガをしたり、運動自体が嫌になったりします。
なので皆さんには私が実際に行っている対処法をご紹介したいと思います。
急な運動でよく痛みが出る膝の場所とその対処方法
先ほど「ついついやり過ぎてしまって」と書きましたが、まさに痛みの原因はそれなんです。
以前のような運動量がこなせるんじゃないかと思ってしまったり、夢中になったりしてついやり過ぎてしまいます。
このやりすぎを“オーバーユース”って言います。
これによって詳しくどこが痛むのかを先に知りたい方はこちら。
さて、やり過ぎて膝が痛くなるとき、よく痛くなるのが、膝の前がわ。
膝小僧です。
私の場合は膝のお皿が痛くなります。
そんな時に役立っているのが、サポーターです。
「なんだサポーターか、当たり前じゃん」って思う方もいるかと思いますが、問題はこの症状にどんなサポーターが良いかですね。
私がよく使っているのがZAMSTさんのサポーター。
しかも大きなけがでもないので、すっと履けるスリーブタイプ
 短くてもお皿を安定させてくれれば大丈夫
短くてもお皿を安定させてくれれば大丈夫これは何年も前に買ったものなので、現在は売ってないかもしれません。
今ZAMSTさんで販売しているスリーブタイプの膝サポーターは下のタイプ↓
私のものよりはちょっと長いですが、全然大げさなサポーターじゃないので、気軽に使えます。
なんなら仕事とか家事の間にも使えますよ。

痛みが起きているところが膝のお皿の周りなので、そのお皿を安定させてくれることが大切です。
なので、このメーカーのものでなくても、お皿の周りを安定させてくれるようにしてくれているものやお皿の動きを安定させてくれるとか書いてあるものを選んで使いましょう!
私の場合は、価格も高くないし、いつもうまく効いてくれているのでZAMSTを使っています。
ふくらはぎの痛む場所とその対処方法
これも主な原因はオーバーユース。
下腿三頭筋といういわゆるふくらはぎの筋肉が悲鳴を上げて痛みを発しています。
ちなみに、ふくらはぎの反対側のすねのあたりもオーバーユースで、痛みがでることがよくあります。
この症状をシンスプリントと言いますが、これについては今回は割愛いたします(いつか説明したいと思います)。
このふくらはぎの痛みを和らげつつ運動をさせてくれるのが、やっぱりサポーター。
これもスリーブタイプ(下の写真は実際使っているもの)。
 これはZAMSTさんの商品とは違いますが、しっかり圧迫してくれます
これはZAMSTさんの商品とは違いますが、しっかり圧迫してくれますちなみにZAMSTさんのふくらはぎ用サポーターはこちら。
薄型なので、こっちの方が気にならないかも。

私の場合は、これを履くだけでだいぶ走りやすくなります。
これだけだと何となく妙な格好になるなって思われる方は、この上からスポーツレギンスやスポーツ用のロングタイツを履くことをお勧めしますよ。
塗り薬や湿布薬は冷たいのが良いの?あったかいのが良いの?
さらに運動した後のケアとして塗り薬を塗っておくこともお勧めします。

私の場合は、運動後にこれを塗っておいて、次の日の痛みがだいぶ軽減されます。
なんか痛いなぁって時は、大体塗るのを忘れていたりしてました。
ところで、湿布はどうなの?って思う方もいるでしょう。
湿布は剥がれたり、特に膝は曲げ伸ばしをする場所なので多少なりとも気になるので、私はあんまり使ってません。
あと話はそれますが、病院に勤めていた時によく聞かれたのが、「湿布って温めるものと冷やすもののどちらがいいんですか?」という質問です。
私は「ヒヤッとする方でいいと思いますよ」って答えていました。
なぜなら温める湿布は湿布自体が暖かくて患部を温めているわけではなくて、そのシップの成分が患部を暖かくなるようにしていて、人によっては刺激によってかぶれやすいと言われているからです。
また、ヒヤッとする成分が痛みを緩和する役割も担っています。
塗り薬もそうですが、今回の場合はヒヤッとするやつがいいと思います。
慢性的な痛みであれば、温めた方が良いのですが、お風呂やレンジで温める湯たんぽ的なもの(米ぬかや小豆でできているもの)で温めるのをおススメします。
自分でできる簡単マッサージ
自分でできる簡単なマッサージがあります。
しかも、マッサージってほどのものでもなく手軽で簡単です。
その名も「パテラモビライゼーション」!
膝のお皿を英語で“patella(パテラ)”と言います。
モビライゼーションは関節のマッサージのようなものです。
やり方は簡単👍
下の写真のように膝を伸ばした状態で完全に脱力します。
ベッドや床、ソファの上がやりやすいでしょう。
 パテラモビライゼーション
パテラモビライゼーション次に自分のお皿を探します。
完全に脱力した状態でお皿に触ってみると上下左右にグラグラな状態であることが分かります。
もしお皿が動かない時は力が抜けていない状態です。
ゆっくりと深呼吸をして、しっかりと脱力しましょう。
お皿の位置が分かったら、左右の手の親指をお皿の上下に当てて、お皿を上下に押し出すように動かします。
これを繰り返すだけ。
結構気持ち良くないですか?
特に何分やってないといけないということもないので、暇を見つけたらやる、ぐらいの感覚で気軽に続けましょう。
いったい何が痛みを発しているのでしょう
膝の痛みを発しているのは?
膝の痛みと言えば、高齢者なイメージもありますが、スポーツなどでもしょっちゅう起こる痛みの一つです。
しかも今回の私のように膝前方の痛みが多いと言われています。
それでは詳しくどこが痛むのか、と言いますとお皿の裏側とお皿が接している大腿骨の部分やその周りが痛むんです。
 膝蓋骨と大腿骨の接している部分やその周りの組織が使い過ぎで痛む
膝蓋骨と大腿骨の接している部分やその周りの組織が使い過ぎで痛むその場所を膝蓋大腿関節と言います。
先ほどマッサージで触ってもらったときに分かったと思うんですが、意外とお皿って不安定なんですよね。
それをサポーターがお皿の動きを安定させてくれます。
そのお皿を安定させてあげることでストレスが減って痛みの軽減が図れるという仕組みです。
ふくらはぎの痛みを発しているのは?
ふくらはぎ痛は、下腿三頭筋と呼ばれる筋肉が使い過ぎで痛みを発していたのが今回の原因。
 ふくらはぎの後面図
ふくらはぎの後面図上の図の腓腹筋内側頭・外側頭、ヒラメ筋を合わせて下腿三頭筋と呼びます。
この筋肉は、ランニングの推進力を生むのに大事な筋肉ですし、踏ん張った時にも非常に大きな力を発揮します。
そこをサポーターで圧迫してあげると筋肉が使いやすくなって、血流も促せるため、痛みも軽減します。
しかも、動きやすくもなりますよ。
まとめ
皆さんどうでした?
急に運動を始めて(再開して)同じような症状が出た人は試してみてもいいかなと思います。
運動をするときの肝となる膝とふくらはぎは使すぎ(オーバーユース)によって痛みを生じやすいところです。
しかし、痛みが出てからすぐにサポーターや塗り薬、湿布、マッサージで対応することで、回復を早めて運動が嫌にならずにすみます。
痛みが再発しやすい人は、予防的にサポーターを使うのもありですよ。
痛みとうまく付き合って、趣味やダイエットのための運動を継続していくことが大切ですね。
参考文献・サイト:
1)皆川 洋至 : オーバーユースに伴う膝前方の痛み“anterior knee pain”―(1):骨の 過労性障害, 臨床整形外科 49巻5号 (2014年5月)
2)池田浩ら: 下腿・足関節・足部のスポーツ外傷・障害, Sportsmedicine 2010 NO.126
3)冷湿布と温湿布について – 一般社団法人 宮崎県薬剤師会
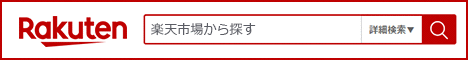
リウマチの方のむくみに効果があると思ったハンドマッサージャーの紹介
みなさん、こんにちは。
ヤジコヤデザインの矢島(代表)です。
ヤジコヤデザインではコーディングなどのデスクワークをしておりますが、実は理学療法士としてリハビリの仕事もやっております。
そんなリハビリ職の視点から、様々な身体のお悩みに役立つ情報をお伝えしていきます。
今回のテーマは前回のEMSに続いて「ハンドマッサージャーを使ったのむくみ改善」です。
今回も、リウマチの方でみられる手のむくみに対して、私見も交えながら書いていきたいと思います。
実際に市販のハンドマッサージャーを使った様子も紹介していきます。
ちなみに前回の記事を見たい方はこちらから↓
「リウマチの方のむくみに効果があると思ったEMSの紹介」
まずは前回のEMSに加えて、ハンドマッサージャーを使った効果を実証
今回紹介するハンドマッサージャー
「ルルド ハンドケア AX-HXL280」
さて今回は、堅苦しい説明は後回しにしてハンドマッサージャーを実際使った様子をお伝えしようと思います。
前回の記事を上げてから翌日からこのハンドマッサージャーを使ってみました。
届いたものはこんな感じ。
 箱の表
箱の表
 箱の裏
箱の裏
中身はこんな感じ。
 シールが付属品でついていて自分好みにデコれます
シールが付属品でついていて自分好みにデコれますボタンは3つで、操作はシンプルです。
主電源のボタンで2つのコースが選べます。
一つは”手を包みもむ「全体コース」”、もう一つは“指を押しもむ「指先コース」”です。
強度は弱・中・強の3段階、ヒーター機能も付いていて、10分で自動で電源が落ちるようになっています。
実際に手を入れた姿がこんな感じ。
パックリ食べられてます(^^)
 実際に手を入れたところ
実際に手を入れたところハンドマッサージャーを実際に使ってみる
~リウマチだから慎重に~
うちの奥さんはリウマチなので、いきなりこいつに手を食べさせるわけにはいきません。
商品のレビューを見てみると、弱でも指が破裂しそうに強い、ともあったので、安全確認のために私が先に使ってみました。
すると、分かったことが下記の2つ。
①確かに中指の圧迫が強くて、中指の先から中身を押し出されそうな感じに圧迫されます。
②「全体コース」よりも、意外と「指先コース」の方がやさしい(弱い)。
①が厄介だなと思いましたが、指を奥まで入れないことで解決できました。
そこで、最終的に落ち着いた使い方がコレ(左の写真)。
 指が反対側から見えない程度に入れる
指が反対側から見えない程度に入れる
 しっかり入れてしまうと中指が痛い
しっかり入れてしまうと中指が痛い
左の入れ方であれば、「全体コース」もやることができました。
ただ、「全体コース」は手のひらへの圧迫が強めなので、様子を見ながら入れる深さを変えることをお勧めします。
「指先コース」であれば、右のように深く入れても大丈夫だと思います。
必ず、“弱”ですよ。
使ってみたら、結構期待できるかも!
さあ、前回の記事にあげたEMSをやった後に、このハンドマッサージャーも使ってみて、6日ほど経過しました。
結果は下の写真のとおり。
 マッサージ直後
マッサージ直後
 前回のEMSのみ
前回のEMSのみ
 何もやってない頃
何もやってない頃
よくなってる!
良かった!
ちなみにハンドマッサージをやって1時間後の写真もお見せします。
 1時間後
1時間後直後よりは戻ってしまっていますが、やっぱりよくなってる。
これは期待ができます!
このハンドマッサージャーはコードレスなんで、手軽に使えて、今のところ苦も無く毎日やれています。
合う合わないがありますので、絶対ではないですが、皆さんも周りの方々に相談してみる価値はあると思いました。

むくみを放置しちゃいけない理由
甘く見ていられないむくみの放置
こんなタイトルをつけると怖くなってしまう人もいるかもしれませんが、ほんとに放っておけないんです。
一般的にリンパ管に何らかの問題があって起こるむくみには徐々に悪化する経過があります。
むくみは浮腫と言いますが、リンパ性の浮腫は下のような感じで悪化します。
潜在性リンパ浮腫 ⇒ 可逆性リンパ浮腫 ⇒ 不可逆性リンパ浮腫 ⇒ 象皮病
リウマチの方で象皮病に至るまでの方は見たことがないので、そこまで行くことはないと思います。
象皮病とは、不可逆性リンパ浮腫の状態が長くなってしまい、組織と組織の間のたんぱく質が編成して繊維網を作って、皮膚までに及ぶ病態です。
皮膚の表面も硬くなって、象の皮膚に似た状態になってしまいます。
先ほども言いましたが、この状態になった方は見たことがないので、ここまで行く可能性は低いと思います。
ただ、不可逆性リンパ浮腫に近いような状態になる可能性は否定できません。
不可逆性リンパ浮腫とは?
不可逆性リンパ浮腫とは、“不可逆性”とある通り、戻らない浮腫です。
通常むくみは朝になると寝るまえよりもよくなっている、なんてことがよくあると思いますが、不可逆性になると朝になってもそれほど軽くなっていません。
さらに、皮膚も徐々に硬くなって、指で押しても凹まなくなります。
組織と組織の間を自由に流れていたたんぱく質や脂肪が変性して沈着し、組織の一部となるためと考えらえています。
むくみ(浮腫)はこうなってしまう前に治療に乗り出すことが大切であると言われています。
まとめ
今回は、うちの奥さんの手のむくみが改善したことがうれしくて、難しいことは少なめに書いています。
まずはこの事実を皆さんにお知らせしたいと思ったので。
むくみ(浮腫)の改善には、「圧迫」「マッサージ」「運動」が大切です。
しかし、これをリウマチの方にセルフケアとしてやってもらうのは非常に難しいです。
それを、EMSやマッサージ器がやってくれれば、うれしい限りです。
個人的には、ハンドマッサージャーが指の変形予防にも効いてくれればなと思っています。
今回、私ども夫婦がやったことは、くれぐれも周りに相談せずにやらないようにしてくださいね。
参考:廣田彰郎 著,「リンパ浮腫の理解とケア」, 学習研究社, 2004
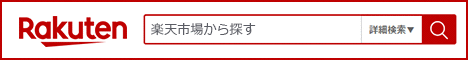
リウマチの方のむくみに効果があると思ったEMSの紹介
みなさん、こんにちは。
ヤジコヤデザインの矢島(代表)です。
ヤジコヤデザインではコーディングなどのデスクワークをしておりますが、実は理学療法士としてリハビリの仕事もやっております。
そんなリハビリ職の視点から、さまざまなカラダのお悩みに役立つ情報をお伝えしていきます。
今回のテーマは「EMSを使ったのむくみ改善」です。
それも、リウマチの方でみられる手のむくみに対して、私見も交えながら書いていきたいと思います。
いつものように、どんなEMSがいいのかも紹介していきます。
むくみのメカニズム
むくみを知るにはまずリンパから
今回もちょっと堅苦しい基本的な仕組みから説明しましょう。
難しい話は後からでいいよって方は、上の目次から「おすすめEMS(手ごろな価格のEMSの実証)」を先に読んでみてください。
むくみのお話をするときによく出てくるのが“リンパの流れ”ですよね。
そのリンパって何ですかね。
人の身体の中は、リンパ管という血管みたいなものが体中に張り巡らされています。
そのリンパ管に流れるリンパ液の流れを“リンパの流れ”っていうんですね。
このリンパ管では動脈・静脈から漏出した組織液を吸収し、体中のリンパ管を経て鎖骨や首あたりで静脈に戻すといったことがされています。
 全身に分布するリンパ管
全身に分布するリンパ管人間の身体の役60~70%は水分であることは有名です。
この水分が体液なんですが、この体液は血液だったり、リンパ液だったり、細胞と細胞の間を満たす組織間液だったりします。
さて、血液は体中をグルグルとめぐっているわけですが、実は毛細血管レベルで1日に約20リットルも漏れ出ています。
でも、そのうち16~18リットルは静脈に再吸収されます。
すると2~4リットルが残ってますよね、これがリンパ液としてリンパ管に入って最終的には静脈へ戻るのです。
つまり、いくつかの原因がありますが、リンパ管の流れが悪くなったり、リンパ管に吸収される水分が少なくなったりするとその2~4リットルの一部が細胞と細胞の間に残って“むくみ”となってしまうのです。
むくみの改善方法
さあ、次はむくみの改善についてです。
もともと人間の身体は代償能力がありますので、たとえリンパ管に障害が起こってもリンパ管のバイパスが発達してむくみを防いでくれます。
ただ、筋肉の運動によるポンプ作用や皮膚からの圧力にも助けられているので、筋力があまり働かなくなったり、皮膚のハリが無くなっていたりするとそのバイパスも生かせないのでむくんでしまいます。
逆に言うと筋肉がポンプの作用として働いてくれたり、皮膚による圧力の代わりとなるもの(弾性ストッキングなど)があれば改善できるというわけです。
そこで今回は、筋肉のポンプ作用による改善に注目していきます。
リンパ管は自動収縮(自分で動く)と受動収縮(他から動かされる)をします。
その繰り返しで吸収したリンパ液を流していきます。
図で説明すると下のような感じです。
 (Weissleder H., Schuchhard C. ed. :Lymphedema Diagnosis and Therapy. p.28, viarital verlag, 2001より改変)
(Weissleder H., Schuchhard C. ed. :Lymphedema Diagnosis and Therapy. p.28, viarital verlag, 2001より改変)自動収縮で流入させて、受動収縮で押し出す感じですね。
受動収縮は、主に筋活動によるものが大きいですが、動脈拍動によっても収縮します。
なので、運動そすると筋肉によって押し出される効果と動脈の拍動が大きくなって増えることで押し出される効果とが期待できます。
さらに、筋活動時のリンパの流れは4~20倍といわれています。
これはどんどん筋肉を動かしてむくみを改善したいなって思いますね。
しかも簡単に。
そこで、活躍するのがEMS(Electrical Muscle Stimulation)です。
次はEMSについて知っていきましょう。
EMSについて
EMSとは
EMSとは Electrical Muscle Stimulation の略で、日本語で言うと電気的筋刺激装置です。
つまり、電気の刺激で筋肉を収縮させてしまう装置です。
その目的は筋肉を電気刺激で収縮させて、筋力強化や基礎代謝量を改善することが目的です。
軽い刺激や収縮パターンによっては末梢循環を促す程度のこともできる機会です。
そもそも筋肉は脳からの指令を受けて動かすわけですが、実はこの指令といいうものは電気信号なんです。
その電気信号を脳ではなく機械がやってくれるので、頑張らなくても運動ができてしまいます。
ただ、よく宣伝とかでムキムキのシックスパックの腹筋が実現できるようなイメージがありますが、これだけでは無理なんです。
脂肪燃焼にはやっぱり有酸素運動が効果的ですので、頑張る必要があります。
しかし、今日の話はむくみ解消。
これは頑張らなくても、EMSからその効果が期待できます。
むくみにEMSが有効なわけ
さきほど、リンパ管は自動収縮と受動収縮によってリンパ液を流している様子を説明しました。
その中の受動収縮の一つに筋活動があったと思いますが、その効果は4~20倍と絶大ですね。
その効果をEMSに期待しようというわけです。
EMSには低周波、中周波、高周波と周波数によって3種類あります。
周波数が0,1Hz~1,000Hzのものが低周波マシンと言われています。
一般的に販売されている家庭用EMSは低周波マシンがメインになり、20Hz~100Hzのものが多いです。
あるサッカー選手や格闘家が宣伝に出演していることで有名なEMSは20Hzです。
皮膚の表層に近いところの筋肉を動かすことができ、EMS特有のピリピリとした痛みを感じることがあります。
ただ、最近は安くてもいろいろと良いものが出てきているので、ピリピリ感は減ってきています。
周波数が1,000Hz~10,000Hzのものが中周波マシンと言われています。
家庭用EMS、業務用EMSどちらにも存在しており、低周波マシンよりも深い皮下2~3cmまでアプローチすることができます。
より深層にアプローチしたい体幹筋強化に適しているかもしれません。
低周波マシンに比べるとピリピリとした痛みは感じにくくなっています。
周波数が10,000Hz以上のものが高周波マシンと言われています。
深層約10cmまでアプローチすることができ、中周波マシンよりも自分では動かすことが難しいインナーマッスルを動かすことが可能です。
周波数や出力が高いマシンは知識や技術を持った人間じゃないと操作ができないため、このタイプは家庭用はあまり見かけません(私は見たことがありません)。
ただ、今回はむくみに対する改善の効果なので、インナーマッスルまでアプローチできなくても大丈夫!
家庭用の低周波EMSで十分だと思います。
なぜリウマチの方のむくみに良いのか
ここまで読んでいくと、まぁどんな人にもEMSでむくみ改善の可能性はあるじゃないか、と思いますね。
そうなんです、どなたにでもその効果は期待できます。
ここで“リウマチの方のむくみに”と言っているのは理由があります。
リウマチの方々はもう薄々お分かりだとは思いますが、EMSを使う一番の利点は、自分で運動をしなくてもいいので関節に負担をかけずに行えるということです。
僕の奥さんもリウマチなんですが、適度な運動をして筋力を落とさずに自分の身体をケアしていくことが大事ということはわかっています。
しかし、その日の体調にもよりますし、続けてやることでどこかが痛くなったりすることもあるので、僕たちがこれくらいなら大丈夫かなと思ったケアの方法でも続けていくとどこかが痛くなってくる、なんてことはよくあります。
ですがっ!
なんせEMSは頑張らなくていいんです。
EMSが頑張ってくれるんで。
しかもモードと強度を適切に調整すれば、関節もほとんど動かなくてすむ(指はわずかに動きますが)ので関節を痛める可能性も極端に少なくてすみます。
これが、僕がリウマチの方に勧めたい大きな理由です。
ただ、気を付けたいところもあります。
それはむくみが生じる理由です。
リウマチの方のむくみの原因として、前述したように“筋力低下”と“皮膚のハリの低下”がありますが、もう一つ大きな原因があります。
それは、炎症です。
関節などで起こる炎症とともにリンパ管にも炎症が起こり、リンパ管の機能低下が起こってしまいます。
もちろん、医療的にも電気刺激を用いたむくみの軽減は適応内ではありますが、炎症がある部位には禁忌もしくは注意すべきとされています。
それは、過剰に電流が流れる可能性があるからです。
必ず、炎症が収まっている時期であることを主治医に確認して、EMSを使用することについて了解を得るようにしましょう。
さぁ、いよいよEMSの紹介です。
おすすめEMS(手ごろな価格のEMSの実証)
お手頃価格のEMS 「EMSIC EMS」
有名なEMSだと何万円もして、ちょっと手が出せないなって思っていたので、お手頃な価格のEMSを買ってみました。
「EMSIC EMS」をネットで7千円(セット価格)くらいで購入。
腹筋用と小型のEMSベルト2つがセットになっていて、実際のものは下のような感じ。
 購入した小型のEMSベルト
購入した小型のEMSベルト楽天で検索してみると下のような感じで売っています。

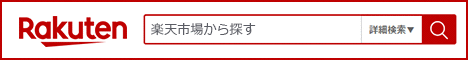
もともとは腹筋用がメインで売られています。
腹筋用も合わせて使っていただいてもいいし、旦那さんが使ってもいいと思います。
でも、7千円くらいで腹筋用も手に入るのはとても良かったと思っています。
実際に腹筋用は僕も使っていて、低周波ですが全然痛くないし、結構効いてる感じで腹筋が収縮します。
でも今回使うのは小型のほうだけです。
この小型は、腕だけじゃなく、太ももにもお尻にも使えます。
次に実際の使用例を紹介していきます。
お手頃EMSを実際に使ってみて
さて、それでは実際に使ってみましょう。
張り付ける場所はこんな感じ。
 パッドの貼付位置
パッドの貼付位置前腕と2つのパッドで挟み込むように貼るんですが、今回は内側の柔らかく大きな筋群を挟み込むように貼ってみました。
この筋肉は指や手首を動かす筋肉たちなんですが、リウマチを持っているとそのあたりが痛みなどで使えないので弱ってしまいます。
実際うちの奥さんも弱っていて、プルプルの二の腕のような状態になっていました。
で、5日間ほど使用した結果がコレ。
 使用前
使用前
 使用後
使用後
使用前は結構むくんでいたんですが、5日後には右のような感じで少し改善が見られました。
指の付け根の拳を作る関節がはっきりしてきて、手首の形も出てきました。
このマシンには6つのモードと9つの強度があります。
今回使ったモードは“MODEⅠ”で、強度は“2”でした。
MODEⅠは「周波数均一、緩やかなリズム、筋肉を按摩し、筋肉をリラックスさせます」と説明書には書いてあります。
この「緩やかなリズム」というのが大事だと思います。
緩やかなリズムでリンパ管を刺激して流れを促進する感じです。
強度2は筋肉がぴくぴくと動いて、指がわずかに動く程度の強度です。
個人差はあると思いますが、これ以上上げるとしっかりとした筋収縮が起こってしまい、指や手首に負担をかける可能性があったので、これくらいで止めました。
これに合わせて、新しくハンドマッサージマシンも購入したので(この時点ではまだ未配送)、それの使用感も皆さんに報告できればと思います。
あと、EMSを使っていて気になってくるのはパッドの劣化です。
その辺は下記のリンクでパッドのお手入れの方法を紹介しているので、参考にしてみて下さい。
「低周波治療器のパッドの寿命を延ばすお手入れ方法とは」
まとめ
EMSは筋力増加だけでなく、むくみ解消としても役に立つツールとしてたくさん売られています。
ご自分の状態をしっかり把握して、無理して使わなければ、リウマチの方々にも非常に役立つものである可能性があります。
むくみを解消するには筋活動と皮膚からの圧力(皮膚のハリ)が大切で、EMSはその筋活動によるむくみ改善を助けてくれます。
ただ、リウマチの方は炎症状態に気を付けて、主治医とご相談のうえで使用することをお勧めします。
もし、「使ってみようかな」と思ってくれた方は、楽天とかで売っているので検索してみてください。
これからも皆さんのお役立ち情報を専門職の立場からお伝えできればと思いますので、「こんなことを書いてほしいな」っていうリクエストがあれば、Twitterの方からでも教えてください。
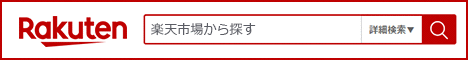
参考:廣田彰郎 著,「リンパ浮腫の理解とケア」, 学習研究社, 2004
木村浩彰ら, 運動障害以外の疾患に対するエビデンスに基づいた電気刺激療法, Jpn J Rehabil Med 2017;54:590-595


























